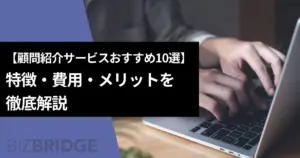- 当記事に含まれる広告と評価について
DXの必要性とは?実施する5つの理由や成功事例について解説!

近年、日本のビジネスシーンでは「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が広く浸透しつつあります。ビジネスパーソンの間で一種のトレンドとなっている側面もありますが、経済産業省もDXを積極的に推進しており、補助金制度の公募などからも、その注目度の高さがうかがえます。では、なぜそこまで国がDXを推進しているのか、そしてなぜ今、DXが必要とされているのでしょうか。
本記事では、そもそもDXとは何か、そしてDXを活用した戦略や事例についてわかりやすく解説していきます。
そもそもDXとは?
そもそも、DXとは具体的にどのようなもので、「IT化」や「デジタル化」といったワードとは何が異なるのでしょうか。
DXの定義
改めて、DXは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略であり、直訳すると「デジタルな状態に変化していく、形を変えていく」といった意味になります。英語圏では、接頭辞の「Trans」を「X」とする習慣があり、Digtalの頭文字と合わせてDXと呼ばれています。具体的な定義としては、デジタル化を通じて業務効率化やイノベーションを起こし、中長期的な企業の競争力を高めることがDXです。
IT化とは異なる
DXに近しいワードとして、「IT化」「デジタル化」といったものが挙げられます。IT化とデジタル化はほぼ同じようなニュアンスで用いられますが、IT化・デジタル化とDXは大きく異なります。DXは、あくまでデジタル技術を活用してイノベーションを起こして企業の競争力を確保することであるのに対し、IT化/デジタル化はデジタル技術を活用することそのものを指しているからです。DXを行うための手段としてIT化、デジタル化があるという関係性になります。
DXはなぜ必要なのか?
ここまでDXの具体的な内容を紹介しました。ここでは、DXの必要性が高まった背景や理由について詳しく解説します。
DXのニーズが高まった背景とは?
DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションが推奨されるようになった背景には、近年の「第4次産業革命」とも呼ばれる急速なデジタル化の進展があります。特に2010年以降、スマートフォンやSNS、電子マネーの普及など、私たちの日常生活においてもデジタル化が急激に進みました。こうした時代の流れの中で、ビジネスの在り方も変化を求められるようになり、それに応える形で生まれたのがDXという概念であり、その根底には「ビジネスを継続的に発展させていく必要性」という思想があります。
DXを推進する目的とは?必要な5つの理由を解説
DXが必要な5つの理由について順に解説します。
1. 従業員が働きやすい環境づくり
まず、DXとは働き方改革に密接に関係しています。DXを通じて業務効率化が進むことで、結果的に従業員が不要な仕事に時間を割く必要がなくなり、働きやすい環境が生まれます。例えば、チャットツールやテレビ会議ツールのようなWebアプリを充実させてリモートワーク制度を導入することで通勤時間が削減されたり、子育てがしやすくなったりします。このように、DXは働き方改革と密接に関係しており、従業員が働きたいと思える魅力的な環境づくりに必要です。
2. 変化に対応できる組織を作る
BCP(Bussiness Continuity Plan)という概念があります。これは、事業継続計画という意味であり、災害などを含む様々な変化に対応するために作成されます。災害などのトラブルがあったときに完全に業務が止まり売上がゼロになってしまうことを防ぐためです。DXを活用することで変化に対応しやすくなり、不測の事態で事業が停止してしまうリスクを最小限に抑えることができます。2020年以降のコロナウイルス感染症の蔓延下において、リモートワークを導入している企業はまさに変化に対応できる組織だと考えられます。
3. 業務の効率化
既存のさまざまな業務は、DXによって効率化が可能です。たとえば、RPAツールの導入によって定例資料の作成を自動化したり、営業管理システムを導入して営業社員の動向を一元管理したりすることができます。このように、働き方改革やBCP策定といった全社的な取り組みでなくても、DXを推進することで、より小さな単位や部門レベルでも業務効率化を図ることが可能です。
4. ビジネスの拡大
DXは業務効率化や働き方改革にとどまらず、ビジネスの拡大や多様化にもつながります。たとえば、リモートワーク環境下での営業活動では、単なる効率化にとどまらず、従来であれば地理的な制約によりアプローチが難しかった遠方の企業にも営業をかけることが可能になります。
5. 「2025年の崖」の対策
経済産業省が提唱する概念に「2025年の崖」があります。これは、日本企業が2025年までにDXを十分に活用できなかった場合、本来得られるはずだったイノベーションや業務効率の向上による機会を失い、加えてレガシーシステムの老朽化によるメンテナンスコストの増大などが重なり、莫大な経済的損失が発生する可能性があるという危機感を示したものです。つまり、DXは将来の日本経済の持続的成長に不可欠な取り組みであるといえます。
DXを推進する前に注意すべき点
DXに対する理解を広める
DXは、全社的に多くの社員が関わるプロジェクトです。そのため、社員一人ひとりの理解を得ないまま推進しようとすると反発を招き、失敗に終わるケースも少なくありません。こうした事態を避けるためにも、まずはDXの目的や背景を社内に丁寧に説明し、理解と共感を広げることが重要です。
組織内でDXを推進できる人材の育成と確保をする
また、多くの企業でDXが進まない要因であるDX人材の不足を解消することが大切です。DX人材を採用するのが難しい場合には、顧問(プロ人材)のサービスなどを活用するのがおすすめです。社員として採用することはできないものの、最先端の知見を持つ一流の人材を必要な期間に応じて活用することができ、コストを抑えつつ最新のノウハウを入手することが可能です。
DX戦略を用いた成功事例
建機・農機などの製品を製造、販売するクボタは2020年に『Kubota Diagnostics(クボタ ダイアグノスティックス)』をリリースしました。こちらは、AR機能や3Dの認識技術を用いた故障診断サービスです。今までは、サービスエンジニアがマニュアルをもとに故障診断を行っていましたが、「診断に時間がかかること」が課題でした。
しかし、『Kubota Diagnostics(クボタ ダイアグノスティックス)』により、故障診断を効率化することに成功しました。この成功事例は、まさにデジタル技術を用いて業務効率化を推進するDXであるといえます。※参考
まとめ
DXは、推進することで働き方改革や業務効率改善につながるだけでなく、新たなビジネス拡大のチャンスにもなる取り組みです。しかし、DXを進めるためのノウハウが社内になかったり、DXに精通した人材を採用できなかったりなど多くの企業ではDX人材の不足から思うようにDXを進めることができていません。
上記のような課題がある場合は、顧問(プロ人材)などを活用して必要な期間だけDX人材の知見を借りるのも一つの手です。気になる方はぜひ顧問(プロ人材)紹介サービスを活用してみて下さい。
引用・参考URL

この記事の監修者
中村 慎也 (アークワードコンサルティング 代表)
大学卒業後、シスコシステムズにてパートナー企業開発や金融業界向けコンサルティングセールスに従事。その後、人材業界大手のインテリジェンス(現パーソルキャリア)でIT業界向け人材紹介や転職サイト「doda」の立ち上げを経験。ヘッドハンティングでWeb系スタートアップの取締役を歴任した後、2018年にアークワードコンサルティングを創業。IT/Webと人材領域の知見を活かし、Web戦略から施策実行・継続改善まで総合的に支援。フリーランスや副業など多様な人材活用分野で10年以上のマーケティング支援実績を持つ。