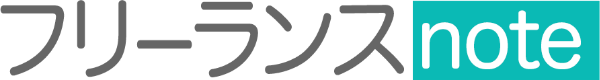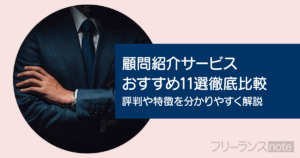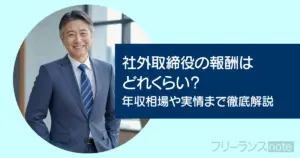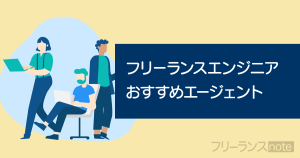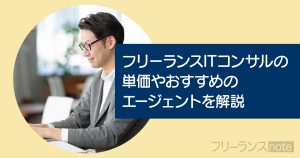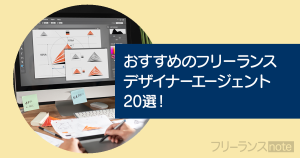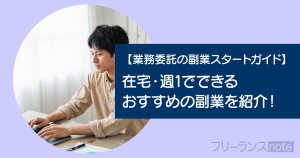- 当記事に含まれる広告と評価について
顧問として働くには?仕事内容や紹介サービス、年収相場まで徹底解説!

「これまでの経験や人脈を活かして、企業の成長に貢献したい」「本業の傍ら、専門性を活かして副収入を得たい」など、そんな想いから“顧問”という働き方に関心を持つ人が増えています。しかし、顧問の実際の仕事内容や年収、どうやって案件を得るのかは意外と知られていません。
本記事では、顧問の定義や種類、年収の相場、信頼できる紹介サービスの選び方まで、初めてでも分かりやすく解説します。
| ・顧問の種類は? ・フリーランスや副業でも顧問になれる? ・顧問の年収の相場は? ・顧問紹介サービスの活用法は? |
そのほか、顧問として成功するためのポイントや副業として顧問活動する際の注意点についても解説していくため、顧問として働くことに興味関心を持っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
INDEX
顧問とは?その役割と基本知識
「顧問」と聞くと一見曖昧な印象を受けがちですが、近年では企業の課題解決や意思決定を支える重要なポジションとして注目されています。特に経験豊富な人材を外部から迎えることで、組織の知見やネットワークを強化する目的があります。本業として活動する人もいれば、副業やフリーランスとして関わる人も多く、働き方は多様化していることもポイントです。
ここでは、顧問の定義や具体的な業務内容、他の役職との違い、必要とされるスキル、企業がなぜ顧問を必要とするのかを解説します。
顧問の定義と一般的な業務内容
顧問とは、特定の分野における豊富な知識や経験を持ち、企業に対してアドバイスや支援を行う外部の専門家を指します。顧問の業務内容は多岐にわたり、経営戦略の助言、営業支援、人材育成、新規事業の立ち上げ支援などが代表例です。業務委託契約の形をとることが一般的で、非常勤での関与が多く見られます。
また、実務に深く関わるケースもあれば、定期的な打ち合わせや会議への出席を中心とするケースもあり、企業との合意内容に応じて柔軟に役割が決まります。
社外取締役・アドバイザーとの違い
顧問と混同されがちな役職に「社外取締役」や「アドバイザー」がありますが、それぞれ法的な位置づけや責任範囲が異なります。社外取締役は、取締役会に出席して企業の意思決定に関与し、一定の法的責任を負う役職です。
一方、アドバイザーはよりカジュアルな立場で助言を行うことが多く、契約や責任の有無が不明瞭な場合もあります。顧問はその中間に位置する存在で、一定の業務内容と報酬を明確にした契約のもと、企業と継続的な関係を築く点が特徴です。
どんな人が顧問になれるのか?必要なスキル・経験
顧問になるには、必ずしも特定の資格が必要というわけではありませんが、企業が信頼できる実績と専門性を持つことが求められます。例えば、経営経験者や大手企業で部長以上を務めた人材、または専門的な技術・法務・人事などの知見を持つ人が多く起用されています。
また、豊富な人脈や業界知識、柔軟なコミュニケーション能力も大きな武器です。企業に対して「何をもたらせるか」を明確にできる人こそ、顧問として選ばれやすい傾向があります。
企業が顧問を雇う理由
企業が顧問を雇う大きな理由のひとつは、外部の専門的な視点や実践的な知見を取り入れ、自社の課題をより効果的に解決するためです。例えば、新規市場への参入時にその分野の第一人者を顧問に迎えることで、戦略やネットワークの構築がスムーズになります。
また、営業活動においては、顧問の人脈を活かして大手企業との接点を作ることも期待されます。こうした“信頼される外部の目”としての存在は、組織にとって極めて重要であり、短期間での成果にも直結することが多いのです。
顧問の種類と働き方
顧問としての働き方は、ひとつではありません。定年後のセカンドキャリアとして本業で働く人もいれば、本業を持ちながら副業として関わる人も増加しています。
また、近年ではフリーランスとして複数の企業と契約を結ぶスタイルも注目されており、それぞれにメリット・デメリットがあります。さらに、「社外顧問」と「社内顧問」といった立場の違いも理解しておくと、活動の幅を広げる際に役立つでしょう。
ここでは、顧問の代表的な種類と働き方について解説します。
①本業としての顧問
顧問を本業として働く人は、経営層や業界の専門家など、高度な経験や知識を持つ人が多く、1社に深く関与するケースが主流です。中小企業の経営支援や、事業立て直し、新規事業開発など、会社の成長に直結するプロジェクトに携わることが多いのが特徴です。報酬水準は高めで、月額数十万円以上を得る例も珍しくありません。
定年退職後のキャリア継続として顧問職に就く人も多く、長期契約を前提に安定した収入を得られることも魅力といえるでしょう。
②副業・兼業としての顧問
近年、週1〜2日の稼働で顧問として活動する副業・兼業型の働き方が広がっています。特に大手企業での実績や専門スキルを持つ人が、自身の知見を外部企業に提供する形で活動しています。
時間的な制約があるため、アドバイザー的な役割にとどまることもありますが、企業にとっては的確な助言が得られる貴重な存在です。副業としての顧問活動は、キャリアの幅を広げたり、報酬を得ながら学びを深めたりする機会としても人気を集めています。
③フリーランス型顧問
フリーランス型の顧問は、企業と業務委託契約を結び、複数社と同時に関わるスタイルです。高度な専門性を武器に、自ら案件を選択し、柔軟に働ける自由度の高さが魅力です。
例えば、スタートアップの技術顧問として複数のプロジェクトに関与するケースや、マーケティング戦略を各社に提供するフリーランス顧問も存在します。自己管理力が求められますが、報酬交渉も可能で、稼働時間と収入のバランスを自分で調整できる点が特徴です。
社外顧問と社内顧問の違い
顧問には「社外顧問」と「社内顧問」があり、それぞれ立場や役割に違いがあります。社外顧問は、企業の外部から専門知識や人脈を提供する立場で、独立性を保ちながら助言や支援を行います。
一方、社内顧問は、かつてその企業に在籍していた元役員や管理職が引き続き顧問として関与するケースが多く、社内事情に精通している点が強みです。企業によっては両者を併用し、外からの知見と内からの理解をバランスよく活用しています。
顧問の年収・報酬体系
顧問として働くうえで気になるのが報酬体系や年収の相場です。業務委託契約で働くケースが多いため、正社員のような月給制とは異なり、稼働日数や業務内容によって大きく変動します。また、近年では成果報酬型の契約や、複数企業と契約して高収入を実現するフリーランス型顧問も増えており、柔軟な働き方と報酬設計が可能です。
ここでは、顧問の年収相場や高額報酬の条件、税務処理の注意点などを解説します。
月額報酬の相場
顧問の月額報酬は業種や職種、稼働時間によって大きく異なります。例えば、経営戦略や人事領域では月10万〜50万円程度が相場とされ、営業顧問では5万〜30万円程度のケースも多く見られます。技術顧問やIT系では専門性が高いため、月額50万円以上の契約も珍しくありません。
なお、週1回・月4回の稼働が標準的な契約条件とされ、企業との交渉次第で柔軟に調整できます。自身のスキルや業界経験を正しく把握し、適正な報酬設定をすることが重要です。
成果報酬型の契約事例
成果報酬型の契約では、一定の成果やKPI達成を条件に報酬が支払われるスタイルが一般的です。例えば、営業顧問が新規顧客を獲得した際に1件あたり数万円〜十数万円の報酬が発生するケースや、資金調達・M&A支援において成功報酬として売却金額の数%を受け取る事例もあります。
こうした契約は企業にとってコストリスクが低く、顧問側にとっても成果が収入に直結するため、実力次第で高収入を目指せる働き方です。トラブルを回避するためにも、交渉時には成果の定義や支払時期を明確にすることが重要です。
年収1,000万円超のケースも?高額報酬の条件とは
顧問として年収1,000万円を超える人も珍しくありません。特に複数の企業と契約するフリーランス型や、専門性が極めて高い技術・法務・経営戦略系の顧問は高収入を得る傾向にあります。
また、大企業やグローバル企業の案件は報酬水準も高く、月額50万円以上の案件が複数あれば年収1,000万円に到達するのは現実的です。さらに、CxO経験や業界での知名度、圧倒的な実績を持つ人材は、紹介サービスでも引く手あまたです。報酬を上げたい人は、強みの明確化と実績の発信を意識しましょう。
顧問報酬の税務処理・確定申告の注意点
顧問報酬は、基本的に業務委託契約に基づく「給与所得」または「事業所得」として扱われ、給与所得とは異なる税務処理が必要です。副業として活動している場合でも、年間20万円を超える収入がある場合は確定申告が必要になります。経費として認められる範囲(交通費、資料代、通信費など)を把握しておくことで、節税効果も期待できます。税務処理を正確に行うためには、税理士への相談や会計ソフトの活用がおすすめです。
顧問紹介サービスの活用法
顧問として働きたいと考えたとき、最も効率的な方法が「顧問紹介サービス」の活用です。これは企業と顧問希望者をマッチングする支援サービスで、登録することで希望条件に合う企業との接点を得やすくなります。顧問としての実績がない人でも、紹介会社を通じて活動をスタートできる点が大きな魅力です。
ここでは、顧問紹介サービスの基本的な仕組みや、信頼できる会社の選び方、選ばれるために意識すべきポイントについて解説します。
顧問紹介サービスとは?仕組みとメリット
顧問紹介サービスとは、企業が求める専門性や経験を持つ人材と、顧問として働きたい人をマッチングする仲介サービスです。登録後にエージェントやコンサルタントとの面談を行い、条件に合致した企業を紹介してもらう形が一般的です。報酬交渉や契約の手続き、業務内容の調整なども代行してくれるため、初めて顧問を目指す人にとっては安心して活動を始められる環境が整っています。
また、非公開求人にアクセスできる点や、専門領域に合った企業を効率的に見つけられるのも大きなメリットです。
信頼できる顧問紹介会社の選び方
顧問紹介会社は数多く存在しますが、信頼できるかどうかを見極めることが重要です。
選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。
POINT
- 過去のマッチング実績
- 登録顧問の職種や業界の幅
- 担当コンサルタントの質
- 企業との取引数や継続率
また、無料でサポートを受けられるか、報酬体系が明確であるかも重要な判断基準です。複数社に登録して紹介される案件数を増やすのはもちろん、実際に面談を受けて自分との相性を確かめることもおすすめです。紹介実績が豊富で、丁寧なサポートを行う会社を選びましょう。
顧問として紹介されやすくなるためのポイント
顧問として企業から選ばれるためには、自分の専門性や強みを明確に伝えることが大切です。過去の実績や成果を定量的に示した職務経歴書を作成し、自己紹介文では「どのような企業に、どんな支援ができるのか」を具体的に表現しましょう。
特に強調したいのは、問題解決力や人脈、業界知識といった“企業が求める価値”です。また、対応のスピードや丁寧さ、面談時の印象も選考に影響します。紹介会社との信頼関係を築くことで、非公開案件への推薦も受けやすくなるでしょう。
顧問になるまでのステップ
企業から顧問として求められる人材になるためには、計画的な準備が欠かせません。まずはこれまでのキャリアを振り返り、自身の強みや専門性を明確にすることが重要です。そのうえで、魅力的なプロフィールや職務経歴書を整え、企業側が必要とする情報を的確に伝える工夫が求められます。また、顧問紹介サービスへの登録や初回契約時の注意点など、実務的な手続きについても事前に理解しておくことで、スムーズな活動開始につながります。
ここでは、顧問になるまでのステップについて確認しましょう。
自己分析とスキル棚卸し
顧問としての第一歩は、自身のキャリアや実績を客観的に見直すことです。どの分野で専門性があるのか、どんな課題解決に強みを持つのかを具体的に整理しましょう。
特に、過去の成功事例や数字で示せる成果は、企業にとっての安心材料になります。また、どの業界、どの企業規模に貢献できるのかを明確にすることで、ターゲットとする案件が絞りやすくなります。自己分析を深めることで、自信を持って顧問活動をスタートできます。
プロフィール作成と職務経歴書の工夫
企業が顧問候補を選定する際、まず注目するのがプロフィールと職務経歴書です。単なる経歴の羅列ではなく、これまでの実績や専門スキル、支援できる領域を明確に記載しましょう。また、課題解決力やマネジメント経験、プロジェクトの成果など、企業が関心を持つポイントを端的にまとめる工夫も重要です。応募する案件ごとに内容を最適化することで、企業側からのアプローチ率が高まります。
顧問紹介サービスへの登録
顧問案件を効率的に獲得するためには、顧問紹介サービスへの登録がおすすめです。一般的な顧問紹介サービスでは、登録時に経歴や専門分野、希望稼働日数、希望報酬など詳細な情報入力が求められます。サービスによっては事前面談やスキルヒアリングがある場合もありますので、事前に準備をしておくと安心です。複数のサービスに登録しておくことで、案件獲得のチャンスが広がります。安定した収入を得るためにも、自分に合った案件が届く仕組みを構築しましょう。
初回契約時の注意点と契約書の確認事項
顧問契約が決まった際は、契約内容をしっかり確認することが重要です。報酬額や稼働日数、支払い条件、契約期間などの基本条件に加え、業務範囲や守秘義務、競業避止条項などにも注意が必要です。
また、トラブル防止のため、成果報告の方法や契約解除条件についても必ず目を通しましょう。不明点があれば遠慮なく契約前に確認することで、後々のトラブルを回避できますこうした契約の確認に自信がない人は、顧問紹介サービスを活用してサポートしてもらうのもおすすめです。
業種・職種別に見る顧問の活躍事例
顧問としての活躍の場は多岐にわたります。企業が抱える課題や成長ステージに応じて、求められる専門領域も異なるのが特徴です。経営戦略や事業開発をサポートする役割から、営業支援、IT導入、技術指導、人事制度の構築まで、さまざまな業種・職種で顧問が活躍しています。
ここでは、顧問の代表的な分野ごとの具体的な活躍事例を紹介します。
経営戦略・事業開発の顧問
経営戦略や事業開発分野では、中長期的な企業成長に向けたアドバイスを行う顧問が多く活躍しています。新規事業の立ち上げ、市場分析、競合調査、資金調達支援など、経営層に近い立場で意思決定をサポートするのが主な役割です。大手企業で経営企画を担当していた経験者や、スタートアップ支援実績がある人が多く求められます。戦略的な視点と実行力の両方が求められるポジションです。
営業・販路開拓の顧問
営業支援や販路開拓の顧問は、自社製品やサービスの売上拡大を目指す企業から高く評価されています。これまで培ってきた人脈や業界知識を活かし、ターゲット企業へのアプローチ方法や提案資料作成のノウハウ提供、営業同行によるクロージング支援などが主な業務です。また、国内市場に限らず、海外販路開拓のサポートを依頼されるケースも増えています。営業経験豊富で交渉力に自信がある人に向いている分野といえるでしょう。
IT・技術・製造業系の顧問
ITや技術、製造業系の顧問は、業界特有の専門知識や技術力を必要とする企業に重宝されています。システム導入支援、IT戦略立案、業務効率化のアドバイス、技術開発プロジェクトの指導など、幅広い役割が期待されます。
特に、IT分野ではクラウド化やDX推進に関する支援ニーズが高く、製造業では生産性向上や品質管理のノウハウ提供が求められることが多いです。実務経験が豊富な技術系人材にとっては大きなチャンスがあります。
人事・組織づくりの顧問
人事や組織づくりの顧問は、採用戦略、人材育成、評価制度の設計、組織風土改善など、企業の「人」に関する課題解決に貢献します。特に成長フェーズにある企業では、急速な人員拡大に伴う制度設計や、マネジメント層の育成支援が求められることが多いです。
また、ダイバーシティ推進やハラスメント対策、離職防止など、時代に即したテーマへのアドバイスも増えています。人事部門でのマネジメント経験がある方におすすめの分野です。
副業として顧問活動をする際の注意点
近年、副業解禁の流れを受けて、現職に就きながら顧問活動を始める人が増えています。しかし、副業として顧問を行う場合には、事前に確認をしておかなければ思わぬトラブルが発生してしまいます。
ここでは、副業として顧問活動をする際の注意点を確認していきましょう。
勤務先への届け出・副業規定の確認
副業で顧問活動を始める前に、まず行うべきなのが勤務先の就業規則や副業規定の確認です。企業によっては副業自体を禁止していたり、事前届け出や許可が必要なケースもあります。
また、顧問業務が現職の業務内容や競合領域と重複する場合、就業規則違反と見なされる可能性があります。事前に人事部門や上司に相談し、必要な手続きを踏むことがトラブル回避の第一歩です。無許可で活動を始めると、懲戒処分のリスクもあるため慎重に進めましょう。
利益相反・情報漏洩に関するリスク管理
副業として顧問活動を行う際には、現職企業と顧問先企業との間で利益相反や情報漏洩が発生しないよう、細心の注意が必要です。特に同業界や競合企業の支援を行う場合は、双方のビジネス機密に触れることになり、法的リスクが生じます。業務の範囲や内容が明確に分かれるよう、契約時に守秘義務や利益相反防止に関する条項を確認することが重要です。
また、現職のコンプライアンス部門に事前相談し、リスクを最小限に抑える対策を講じましょう。
複数企業の顧問になる場合のスケジュール管理
複数企業と同時に顧問契約を結ぶ場合は、スケジュール管理が非常に重要になります。各企業で求められる稼働時間や業務内容が異なるため、事前に無理のないスケジュールを組むことが必要です。
また、急な打ち合わせや対応が発生するケースもあるため、日常的に余裕を持った時間配分を心掛けましょう。納期やレスポンス速度が遅れると信頼を失う原因となります。Googleカレンダーやタスク管理ツールを活用し、案件ごとの進行状況を常に把握しておくことが大切です。
副業から本業化するケースとその流れ
副業顧問として活動を始めたものの、案件数や収入が増えることで最終的に本業化するケースも少なくありません。副業段階で継続的に案件を獲得できるようになった場合は、まずは収入の安定性や生活費を考慮した上で独立を検討しましょう。
社会保険や税務処理の手続きについても早めに準備が必要です。独立を視野に入れた段階では、顧問契約書の見直しや、新たな営業活動の強化も求められます。計画的にステップを踏むことで、スムーズなキャリア転換が実現できます。
顧問として成功するためのポイント
顧問として長く活躍し続けるためには、単にこれまでの経験を語るだけでは不十分です。企業が求めるのは「実際に成果を出せる人材」であり、そのためには課題解決力や信頼性、継続的なスキルアップ、人脈の構築などが欠かせません。
また、自身の専門分野を明確にし、的確なアドバイスができる体制を整えることも重要です。さらに、トラブル回避のためのリスクマネジメント意識も求められます。
ここで、顧問として成功するためのポイントを解説します。
課題解決力と信頼性が最重要
顧問に最も求められるのは、企業が抱える課題に対して的確かつ実行可能な解決策を示せる力です。理論だけではなく、実務経験に裏打ちされた現実的な提案ができるかどうかが評価の分かれ目です。
また、約束した成果を確実に出す姿勢や、期日を守る誠実さも信頼構築には欠かせません。一度信頼を得られれば、継続契約や別案件の紹介につながる可能性も高まります。顧問活動においては「課題解決力」と「信頼性」が常に両輪であることを意識しましょう。
定期的な情報発信・人脈づくり
顧問としての活躍の場を広げるには、自身の知識や経験を定期的に発信することが効果的です。セミナー登壇、SNSでの情報共有、ビジネスブログの運営などを通じて、専門性をアピールできます。こうした情報発信は、企業側の信頼獲得にもつながり、新たな顧問依頼のきっかけとなることがあります。
また、人脈づくりも重要です。経営者交流会や業界イベントに積極的に参加し、リアルなつながりを増やすことで、口コミや紹介による案件獲得が期待できるでしょう。
専門分野に特化する重要性
幅広い分野での知識を持つことも価値ですが、顧問として安定的に需要を得るためには「この分野ならこの人」と認知される専門性が強みになります。特に、業界特化型のノウハウや特定領域での実績は企業にとって大きな魅力です。自分が得意とする分野を明確にし、職務経歴書やプロフィールにもその強みが一目で伝わるよう工夫しましょう。専門性が明確であればあるほど、競合との差別化ができ、安定した案件獲得につながります。
リスクマネジメントの意識を持つ
顧問活動には情報漏洩、利益相反、契約トラブルなどのリスクが常に伴います。そのため、リスクマネジメント意識を持ちながら行動することが重要です。例えば、企業秘密を守るための情報管理、契約内容の事前確認、業務範囲の明確化など、トラブル防止策を徹底する必要があります。問題が発生した場合の対応策を事前に考えておくことも、長期的な信頼関係維持には欠かせません。
安易な対応が信用失墜につながることを常に意識しましょう。
顧問に関するよくある質問
顧問という働き方に興味はあっても、「自分にもできるのか」「どのタイミングで目指すべきなのか」など、さまざまな疑問を持つ人は少なくありません。実際、顧問として活躍する人の背景や年齢、求められるスキルは多種多様です。
経験豊富なシニア層だけでなく、比較的若い世代でも活躍するケースが増えています。また、どのような人材が企業に求められているのかを理解することで、顧問キャリアへの第一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
ここでは、顧問に関するよくある質問についてQ&A形式で解説します。
未経験でも顧問になれる?
顧問と聞くと「特別な実績がないと無理」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。たとえ顧問としての経験がなくても、特定分野での実務経験や成功体験があれば十分にチャンスがあります。企業が求めているのは、現場で培ったリアルなノウハウや、課題解決に役立つ実践的なアドバイスです。
特に、スタートアップ企業や中小企業では、経営層に近い立場での経験が重宝されるため、管理職経験やプロジェクト推進経験があれば強みになります。自分では価値がないと思っているスキルや経歴でも、企業によっては重宝されるケースもあるため、最初から諦めずに顧問紹介サービスに相談してみましょう。
どのくらいの年齢から目指せる?
顧問という働き方に年齢制限はありません。一般的には40〜60代のシニア層が多い傾向にありますが、近年は30代でも活躍する事例が増えています。
特にITやデジタルマーケティング、ベンチャー支援や人事採用系など、比較的新しい分野では若手の顧問が求められることもあります。重要なのは年齢よりも、これまでのキャリアで得た専門知識や課題解決力、そして企業側のニーズに応えられる実績があるかどうかです。年齢にとらわれず、自分の強みを活かせる分野を見つけましょう。
どんな人材が求められている?
企業が顧問に求めるのは「即戦力として現場の課題を解決できる人材」です。具体的には、特定の業界や職種に精通し、過去に成果を上げた経験がある人が高く評価されます。
また、単なるアドバイスだけでなく、実行支援や人脈活用ができる人も重宝されます。さらに、コミュニケーション能力や問題解決への柔軟な対応力も重要な評価ポイントです。顧問として成功するには、過去の実績をしっかり棚卸しし、企業側が求める「価値提供」ができることを明確にアピールする姿勢が求められます。
まとめ
この記事では、顧問の仕事内容や年収相場、報酬体系や目指すためのステップについて解説しました。
| ・顧問の年収相場 ・顧問になるためのステップ ・顧問として成功するためのポイント ・副業で働く際の注意点 |
顧問として働くには、自身の専門性や経験を活かすことが不可欠です。本業・副業問わず、企業の課題解決に貢献できるスキルが求められます。働き方は柔軟で、稼働時間に応じた報酬を得られる点も大きな魅力です。顧問紹介サービスを活用すれば、マッチングや契約面のサポートも受けられるため、初めてでも安心してスタートできます。
本記事で解説した年収相場や仕事内容を理解し、自分に合ったスタイルを見極めて、顧問としての成功を目指しましょう。
引用・参考URL
参考:BIZBRIDGE | 社外取締役と顧問の違いとは?それぞれの特徴や報酬について徹底解説!
参考:KENJINS | 顧問に求められる必須スキルと役割・仕事内容
参考:あしたの人事 | 顧問とは?報酬相場や役割、どんな仕事なのかをわかりやすく解説参考:顧問ライフ | 顧問の報酬は給与所得と事業所得どちらになるの?

この記事の監修者
中村 慎也 (アークワードコンサルティング 代表)
大学卒業後、シスコシステムズにてパートナー企業開発や金融業界向けコンサルティングセールスに従事。その後、人材業界大手のインテリジェンス(現パーソルキャリア)でIT業界向け人材紹介や転職サイト「doda」の立ち上げを経験。ヘッドハンティングでWeb系スタートアップの取締役を歴任した後、2018年にアークワードコンサルティングを創業。IT/Webと人材領域の知見を活かし、Web戦略から施策実行・継続改善まで総合的に支援。フリーランスや副業など多様な人材活用分野で10年以上のマーケティング支援実績を持つ。