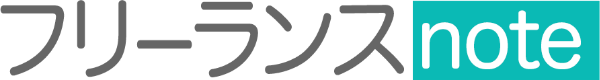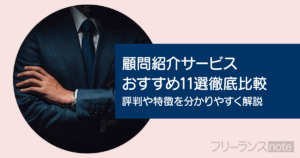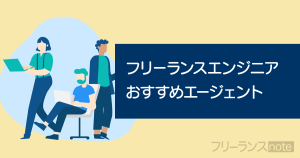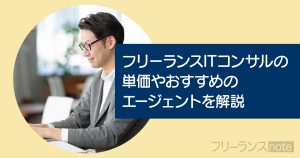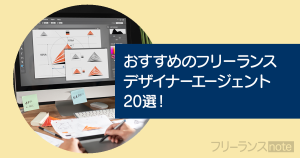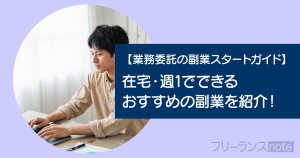- 当記事に含まれる広告と評価について
社外取締役の報酬はどれくらい?年収相場や実情まで徹底解説!
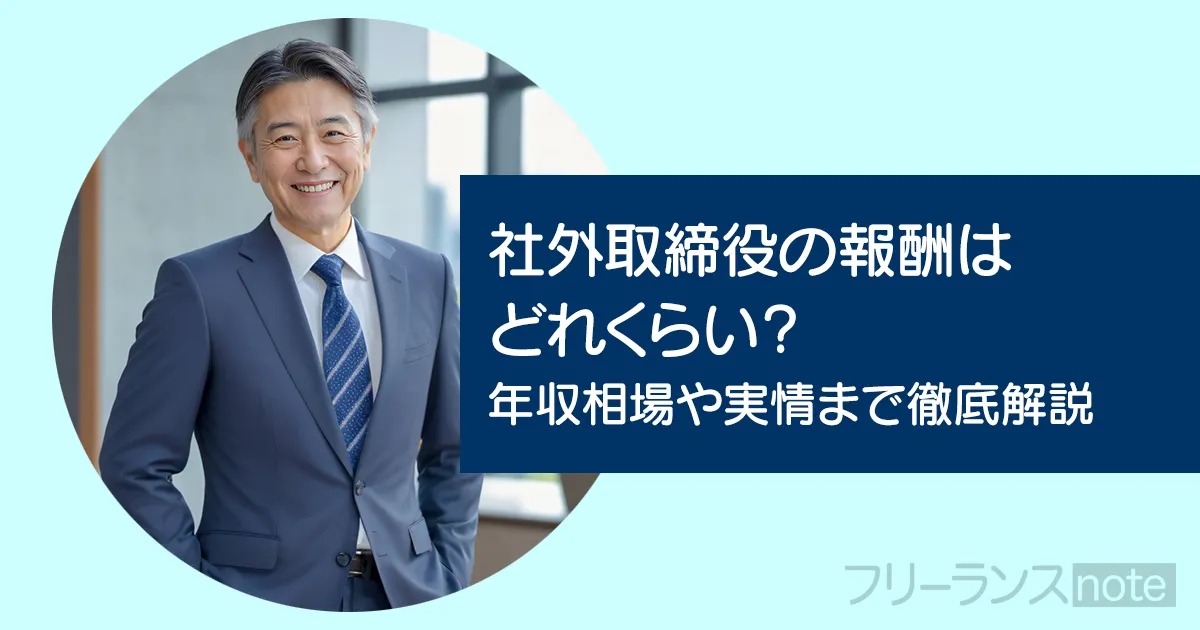
「社外取締役って実際どれくらい報酬をもらえるの?」と気になったことがある人もいることでしょう。非常勤で働けるイメージはあるものの、年収や相場、仕事内容とのバランスについて具体的に知られていないのが実情です。本記事では、社外取締役の平均年収や報酬の仕組み、企業別の実例、フリーランス・副業としての可能性まで詳しく解説します。
| ・社外取締役の報酬はどれくらい? ・社外取締役の報酬体系は? ・フリーランスでも社外取締役になれる? ・社内取締役との違いは? |
キャリアの選択肢として社外取締役に興味を持っている人はもちろん、企業側で登用を検討している人もぜひ参考にしてみてください。
INDEX
社外取締役とは?
近年、企業の経営体制の透明性や健全性が問われる中で、「社外取締役」という存在が注目を集めています。社外取締役は、企業の経営判断に対して客観的な視点から助言や監督を行う役割を担い、社内にいない立場だからこそ、経営のブレを正す重要な役割を果たします。
ここでは、社外取締役の定義や社内取締役との違い、任命の背景やトレンド、働き方の特徴について確認していきましょう。
定義:社外取締役の役割、社内取締役との違い
社外取締役とは、企業の取締役会の一員でありながら、その企業やグループ会社の従業員・役員としての経歴がなく、独立した立場から経営に助言や監督を行う存在です。これに対して、社内取締役は元社員や現経営陣など企業内部から選出されるケースが一般的で、会社内部の視点で経営を進めます。
一方、社外取締役は客観性や中立性を重視し、利益相反のない第三者的立場から経営判断の妥当性をチェックする役割を担います。つまり、社外取締役は企業のガバナンス機能を強化するために不可欠なポジションなのです。
任命の背景と近年のトレンド
社外取締役の任命が活発になった背景には、企業不祥事の抑止や経営の透明性向上といったコーポレートガバナンスの強化が求められていることがあります。特に上場企業では、2021年3月1日から社外取締役の設置が義務化されたため、上場を目指す企業は社外取締役が問われる可能性があるため要注意です。
また、ダイバーシティの観点から女性や外国人、有識者など多様な人材の登用が進んでおり、経営会議に多角的な視点をもたらすことが期待されています。今後も社外取締役の重要性は一層高まり、求められるスキルも多様化していくでしょう。
非常勤であることが多い
社外取締役は、その多くが非常勤として企業に関わります。常勤の社内取締役とは異なり、日々の業務には直接関与せず、取締役会などの重要な会議への出席や経営判断に対する助言・監督が主な役割です。そのため、月に数回の出席や資料確認で職務を果たすケースが多く、他企業の社外役員や本業との兼任が可能な働き方となっています。ただし、報酬を得る以上は責任も伴うため、限られた時間でいかに的確な判断や指摘ができるかが問われます。
このことから、専門性と効率的な業務遂行能力が求められる職務であるといえるでしょう。
社外取締役の報酬体系とは?
社外取締役の報酬は、企業ごとに制度や水準が異なるものの、一般的には基本報酬に加えて会議出席手当や株式報酬などが組み合わされる形で構成されています。フルタイム勤務ではない分、報酬体系は柔軟に設計されており、責任の重さや専門性、関与度に応じて調整されることが多いです。
ここでは、社外取締役の報酬を構成する主要な要素について、それぞれの内容と実態を解説します。
基本報酬
社外取締役の報酬の中心となるのが、年俸制による基本報酬です。非常勤であっても役員としての責任を負うため、年間を通じて一定の金額が支払われます。報酬額は企業規模や業種、社外取締役の専門性や影響力によって異なり、一般的には年300万〜800万円程度が相場とされています。
特に東証プライム上場企業では報酬水準が高めで、ガバナンス強化の重要性が増す中、専門性のある人材への対価として基本報酬が厚くなる傾向にあります。透明性も重視されており、報酬額は有価証券報告書などで開示されるため、興味がある人は上場企業の報酬をチェックしてみましょう。
会議出席ごとの報酬
基本報酬とは別に、社外取締役には会議への出席ごとに支払われる「出席手当」が設けられていることもあります。これは取締役会や指名・報酬委員会など、経営の意思決定に関わる重要な会議に参加するたびに支払われるもので、数万円から十数万円程度のケースが一般的です。
特に会議回数が多い企業や、臨時の経営課題が頻繁に発生する場合には、この手当の比重が高まることもあります。出席手当は実際の稼働量に連動した形で報酬を補う役割があり、非常勤である社外取締役にとっては収入の一部として重要です。
株式報酬やストックオプション
近年の報酬制度では、経営への当事者意識や中長期的な視点を高める目的で、株式報酬やストックオプションを社外取締役に付与するケースが増えていることにも注目です。これにより、取締役の報酬と企業の業績が連動し、株主との利害を一致させるインセンティブ設計が可能になります。株式報酬には譲渡制限付き株式(RS)やパフォーマンス連動型などがあり、企業ごとに仕組みが異なります。
なお、金銭報酬に比べて将来的なリスクや価値変動があるため、社外取締役にとってはリターンと責任のバランスを慎重に見極める必要があります。
交通費や業務経費の支給有無
非常勤として勤務する社外取締役には、交通費や業務経費の実費が支給されることが一般的です。取締役会や重要な打ち合わせのために遠方から移動する場合、交通費や宿泊費の支給があるかどうかは、報酬の実質的な価値にも影響します。企業によっては日当や通信費、資料作成費といった業務関連経費も支給対象となることがあります。
一方で、契約時に経費支給の条件が明記されていないと、自己負担になる可能性もあるため、報酬額だけでなく実費補填の有無も重要な確認ポイントです。トラブルを未然に防ぐためにも、契約書での明文化しておきましょう。
社外取締役の報酬相場
社外取締役は非常勤であることが多く、報酬水準もさまざまです。企業規模や業種、株式市場の区分などによって大きく異なり、一概に「このくらい」と言い切るのは難しいものの、一定の相場感は存在します。また、働き方や専門性によっても年収に幅が生まれ、週1回程度の稼働でも数百万円の報酬が得られるケースもあります。
ここでは、社外取締役の報酬相場や市場別の傾向、非常勤の収入イメージ、高報酬企業の特徴について解説します。
社外取締役の平均報酬
社外取締役の報酬は、上場企業と非上場企業で大きな差があります。一般的に、東証プライムをはじめとする上場企業では、年収500万〜800万円程度が相場とされ、企業によっては1,000万円を超えるケースもあります。
一方、非上場企業では200万〜400万円程度が相場で、報酬の規模は企業の業績やガバナンス体制の成熟度に依存します。上場企業は有価証券報告書で役員報酬の情報が開示されるため透明性が高く、報酬水準も比較的安定しています。対して非上場企業では契約条件も多様で、個別交渉によって差が出やすい点が特徴です。
市場ごとの違い
東京証券取引所には、プライム、スタンダード、グロース及びTOKYO PRO Marketの4市場がありますが、社外取締役の報酬は市場によって明確な差があります。プライム市場は上場企業の中でも最もガバナンス水準が高く、企業規模も大きいため、社外取締役の年収は600万〜1,000万円程度と比較的高水準です。スタンダード市場では中堅規模の企業が多く、400万〜700万円が目安となります。グロース市場はスタートアップや成長企業が中心で、報酬は300万円前後が相場ですが、株式報酬による将来的なリターンが期待される場合もあります。
もちろん、非上場企業であっても上場企業を上回る報酬が得られるケースもあるため、あくまで目安であることを覚えておきましょう。
非常勤の年収イメージ
社外取締役は基本的に非常勤であり、稼働頻度は月1〜数回程度が一般的です。中でも「週1回程度の稼働」であれば、年間300万〜600万円ほどの報酬を得られるケースが多く見られます。業務内容としては、取締役会や委員会への出席、資料の確認、経営への助言などが中心で、実働は月10時間以下という例もあります。副業・兼業が認められていることが多いため、他の業務と並行して収入を得たい人にも適した働き方です。稼働の割に高い年収が得られる点は、社外取締役という役職の大きな魅力のひとつです。
報酬が高い企業の特徴
社外取締役の報酬が高い企業にはいくつかの共通点があります。まず、海外にも事業を展開するグローバル企業は、経営の複雑さやステークホルダーの多さから、高度な知見を持つ社外取締役を必要とし、高報酬を提示する傾向があります。また、M&Aや事業再編を控えている企業、ガバナンス体制の強化が急務な企業なども、積極的に専門家を登用し、それに見合う報酬を支払うケースが多いです。
さらに、企業価値向上に直結する役割が求められる場面では、成果報酬や株式報酬が上乗せされることもあります。
報酬相場の変化と今後の傾向
社外取締役の報酬はこれまで企業の慣習や規模に依存してきましたが、近年はコーポレートガバナンス改革や多様性の推進、グローバル経営への対応などを背景に、そのあり方が大きく変わりつつあります。特に、社外から専門性や独立性を持ち込む役割が強調されるようになり、報酬の透明性や競争力のある水準が求められるようになっていることにも注目です。
ここでは、社外取締役の報酬相場に見られる変化と今後の見通しについて解説します。
コーポレートガバナンス改革による報酬増加傾向
日本企業では近年、コーポレートガバナンス・コードの改訂を背景に、社外取締役の設置義務や独立性の強化が進められています。その結果、形だけの名義職から実質的な助言・監督を担うポジションへと役割が重くなり、それに比例して報酬水準も上昇傾向にあるのです。
特に上場企業では、従来よりも高い専門性を持つ人材を確保する必要があるため、報酬競争力を高める動きが加速しています。また、報酬の透明性を求める投資家の声もあり、有価証券報告書における開示内容も充実しつつあります。
女性社外取締役の登用と待遇の変化
ダイバーシティ経営が注目される中で、女性社外取締役の登用が進んでいます。政府の方針や東証のガイドラインによって、一定数の女性役員の確保が推奨され、各企業が積極的に候補者を探すようになりました。これに伴い、女性候補者の報酬水準も見直されつつあり、性別に関わらず能力や経験に見合った待遇が提示されるようになっています。以前は「形だけの登用」と批判される例もありましたが、現在では実務に即した評価が重視されており、キャリアのある女性にとっては報酬面でもチャンスが広がってきています。
専門人材への高報酬化
企業経営が複雑化する中で、社外取締役にも高い専門性が求められるようになっています。特に、コンプライアンス・法務・財務・ITといった分野での知見を持つ人材は希少性が高く、報酬水準も相応に高まっています。例えば、弁護士や公認会計士、IT戦略に長けたエンジニアなどが社外取締役に就任するケースでは、年収1,000万円を超える報酬が提示されることも少なくありません。専門分野での実績がある人材は、単なるガバナンス強化にとどまらず、経営の意思決定に深く関与できるため、企業としても投資価値があると判断されているのです。
欧米との比較とグローバル水準
欧米と比較すると、日本の社外取締役の報酬は依然として低水準であるという指摘があります。例えば米国では、社外取締役の年収が数千万円規模になることも珍しくなく、株式報酬を通じて長期的な成果へのコミットメントを強く促す仕組みが一般的です。
これに対して日本では、年俸制や出席手当を中心とした保守的な報酬設計が主流ですが、グローバル競争が進む中で、より優秀な人材を惹きつけるためには欧米水準を意識した改革が必要とされています。今後、日本企業も報酬体系の国際的な整合性を意識した見直しを進めることが期待されます。
報酬と責任のバランス
社外取締役は、非常勤であるにもかかわらず、会社の経営判断に深く関わる重要な立場にあります。そのため、相応の報酬を受け取る一方で、法的責任や社会的責任を負うことも避けられません。報酬と責任のバランスは、企業ガバナンスにおいて極めて重要なテーマであり、候補者にとっても十分な理解が必要です。
ここでは、社外取締役に課される法的義務やリスク、またそれに対する対策としての保険活用などについて解説します。
社外取締役の法的責任
社外取締役であっても、法律上は社内取締役と同様に「善管注意義務」や「忠実義務」が課されます。善管注意義務とは、経営判断を行う際に一般的な注意力と能力をもって職務を遂行する責任であり、怠った場合には損害賠償責任が問われる可能性があります。
また、忠実義務とは、会社の利益のために誠実に職務を果たすべきという義務であり、私益を優先する行為は許されません。非常勤である社外取締役でも、これらの義務を果たす責任があるため、報酬の対価としての責任の重さを自覚する必要があります。
報酬に見合う責任とは?
社外取締役の報酬は、月数回の稼働で数百万円以上となる場合もありますが、その背景には重大な経営判断への責任が含まれています。例えば、不祥事を未然に防ぐためのリスク管理や、経営の妥当性を監視する役割が求められます。報酬に見合うだけの責任とは、単なる会議出席にとどまらず、意思決定に対する積極的な関与や、企業の持続的成長への貢献が求められるということです。
高額な報酬を受ける以上、万が一の際には説明責任や監督責任が厳しく問われる立場であることも認識すべきでしょう。
訴訟リスク・損害賠償リスク
社外取締役にも訴訟や損害賠償のリスクは存在します。例えば、企業の不祥事や経営判断の失敗により、株主や第三者から損害賠償請求を受けるケースがあります。特に、内部統制やガバナンス体制が機能していなかった場合には、取締役の監督責任が問われることがあるため要注意です。社外取締役は「外部の目」としての期待が大きいため、監督不十分と見なされれば法的責任を問われる可能性もあります。非常勤とはいえ、実態としては重大な法的リスクを負っており、報酬と同時に責任の重みも理解しておきましょう。
保険(役員賠償責任保険)の活用
これらのリスクに備える手段として、多くの企業では「D&O保険(役員賠償責任保険)」に加入しています。これは、取締役が業務執行に関連して法的責任を問われた場合に、その損害賠償や訴訟費用をカバーする保険です。社外取締役も対象に含まれており、万が一の法的トラブルに備える重要な制度です。
ただし、すべての企業が十分な補償内容を整備しているとは限らないため、就任前には保険の有無や適用範囲を確認することが推奨されます。高額な報酬と引き換えに負うリスクを、適切にカバーする備えが不可欠です。
フリーランス・副業としての社外取締役
近年、働き方の多様化が進む中で、フリーランスや副業という形で社外取締役に就任するケースが増加しています。非常勤であることが多いため、本業を持つビジネスパーソンでも柔軟に関わることが可能です。週に数時間の稼働で高い専門性を提供し、企業のガバナンスや経営判断に貢献できる社外取締役は、副業としても注目を集めています。ただし、情報管理や利益相反などのリスクには十分な配慮が必要です。
ここでは、フリーランス・副業としての社外取締役の実態と注意点について解説します。
常勤ではないため副業との両立が可能
社外取締役は基本的に非常勤の役職であり、常勤のように毎日出社したり、定時で働いたりする必要はありません。そのため、本業を持つビジネスパーソンやフリーランスでも就任が可能で、副業との両立がしやすい点が大きな魅力です。実際に、経営や法律、IT、医療などの専門家が本業の傍ら社外取締役として企業の意思決定に関与する例が増えてきています。企業側にとっても多様な知見を取り入れるチャンスとなるため、双方にとってメリットがある形態といえるでしょう。
週1~2日の稼働で得られる報酬感覚
社外取締役は、週に1〜2回程度の稼働で年収300万〜800万円ほどの報酬を得ることが一般的です。具体的な業務内容は、取締役会や各種委員会への出席、資料の確認、必要に応じた助言やリスクチェックなどが挙げられます。実働時間は月10〜20時間程度というケースも多く、限られた時間の中で専門性を発揮することが求められます。働き方としてはフルリモートも可能なため、他の仕事とスケジュールを調整しながら柔軟に稼働できる点も大きな魅力です。
副業・兼業で社外取締役を務めるケースの増加
最近では、社外取締役を副業や兼業として担うケースが急増しています。特にスタートアップや中堅企業が、社内にない専門的知見を補う目的で、他業種や他社で活躍するプロフェッショナルを外部から招へいする動きが活発です。
また、企業側もフルタイムでの雇用を前提とせず、週数回のアドバイスや取締役会での意見提供を期待するスタイルが一般化してきました。このような副業・兼業のスタイルは、企業の多様性確保にも貢献しており、今後さらに広がる可能性があります。
フリーランス・副業の注意点
副業として社外取締役を務める際に注意すべきなのが、守秘義務や利益相反のリスクです。複数企業と関わる場合、同業他社との機密情報が交錯する可能性があり、情報漏洩や契約違反に発展するおそれがあります。
また、所属先の企業や本業との利害関係が発生する場合には、取締役としての判断の中立性が問われるケースもあるでしょう。就任前には契約内容や守秘義務、利益相反の可能性について明確に整理し、必要に応じて法的アドバイスを受けることが重要です。信頼性と誠実性が強く求められるポジションであることを忘れてはなりません。
社外取締役の報酬に関するよくある質問
これから社外取締役を目指す人はもちろん、現職者においても報酬に対して疑問を感じている人は少なくありません。報酬の決定方法や交渉の可否、成果報酬の有無、退任後の処遇、さらには税務処理の取り扱いまで、気になるポイントは多岐にわたります。
ここでは、社外取締役の報酬に関するよくある質問についてQ&A形式で解説します。
報酬の交渉は可能?
社外取締役の報酬は、企業側があらかじめ設定していることが多いものの、選任時には交渉の余地があります。特に専門性が高い人材や複数社での取締役経験がある場合、自ら希望する報酬水準を提示し、それに見合う業務内容を提示することが一般的です。また、報酬だけでなく、稼働時間や会議頻度、リモート対応の可否なども含めて交渉の対象になります。ただし、株主総会での承認が必要な場合もあるため、柔軟性はあっても無制限ではありません。初回面談の際に誠実に要望を伝えることが交渉成功のカギとなるでしょう。
成果報酬型の契約はある?
社外取締役の報酬は一般的に固定年俸制や出席手当で構成されますが、一部の企業では成果報酬型の制度を導入している例もあります。例えば、企業業績や株価の上昇、特定プロジェクトの成功などに連動して、報酬を上乗せする契約形態が存在します。また、ストックオプションや譲渡制限付き株式(RS)といった中長期的な成果を評価する仕組みが活用されている企業にも注目です。それでも、日本ではまだ少数派であり、成果報酬の導入は企業規模やガバナンス意識の高い会社に限られる傾向があります。
導入の有無は契約前にしっかり確認しましょう。
退任後の報酬はある?
一般的に、社外取締役が退任した後に継続して報酬が支払われることはほとんどありません。ただし、在任中に支給が決定されていた株式報酬やストックオプションが、退任後に権利確定する場合はあります。また、企業が顧問やアドバイザーとして継続的な関与を希望する場合には、別契約のもとで報酬が支払われるケースもあります。
なお、退任慰労金のような支給は現在のガバナンス指針では抑制される傾向にあるため、退任後の報酬に過度な期待は禁物です。
税金はどうなる?
社外取締役の報酬は、基本的に「給与所得」または「報酬・料金」として扱われ、源泉徴収の対象になります。企業との契約形態によっては、給与所得として毎月支給される場合と、報酬・謝金として支払われる場合があり、それぞれ税務処理が異なります。特に複数社から報酬を得ている場合は、確定申告が必要となるケースがほとんどです。経費の扱いや控除の適用範囲など、税務の取り扱いが複雑になることもあるため、税理士などの専門家に相談しておくと安心です。節税対策も含め、スケジュールに余裕を持って準備を進めておきましょう。
まとめ
この記事では、社外取締役の報酬相場、報酬体系や今後の動向についてついて解説しました。
| ・社外取締役の報酬相場 ・社外取締役の相場の今後の動向 ・社外取締役の報酬と責任のバランス ・フリーランス・副業としての社外取締役 |
社外取締役の報酬は、企業規模や業種によって大きく異なりますが、平均では年収300万〜800万円程度が相場です。報酬体系は基本報酬のほか、出席手当や株式報酬が含まれる場合もあります。
近年はコーポレートガバナンスの強化や多様性の推進により、女性や専門性の高い人材の登用が進み、報酬水準も上昇傾向にあります。非常勤・副業としての働き方も可能であり、自身のキャリアを活かして社会に貢献しながら安定した収入を得られる魅力的な選択肢です。
これから社外取締役になる人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
引用・参考URL
参考:役員報酬.com | 役員報酬制度の設計ポイント
参考:GVA法人登記 | 社外取締役の報酬の決め方や相場を紹介
参考:OUTSIDE MAGAZINE | 中小企業における社外取締役の報酬額相場と決め方|社外役員の必要性も解説
参考:AGS | 社外取締役とは?求められる役割や取締役との違い、設置が必要なケースや報酬相場を解説
参考:内山公認会計士・税理士事務所 | 非常勤役員の日当の損金算入の可否
参考:LINE | 社外取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
参考:日本の人事部 | 社外取締役の処遇について
参考:スター綜合法律事務所 | 社外取締役の会社に対する善管注意義務
参考:D&O保険ガイド | 社外取締役を依頼されたら?D&O保険(会社役員賠償責任保険)が必須な理由を解説

この記事の監修者
中村 慎也 (アークワードコンサルティング 代表)
大学卒業後、シスコシステムズにてパートナー企業開発や金融業界向けコンサルティングセールスに従事。その後、人材業界大手のインテリジェンス(現パーソルキャリア)でIT業界向け人材紹介や転職サイト「doda」の立ち上げを経験。ヘッドハンティングでWeb系スタートアップの取締役を歴任した後、2018年にアークワードコンサルティングを創業。IT/Webと人材領域の知見を活かし、Web戦略から施策実行・継続改善まで総合的に支援。フリーランスや副業など多様な人材活用分野で10年以上のマーケティング支援実績を持つ。